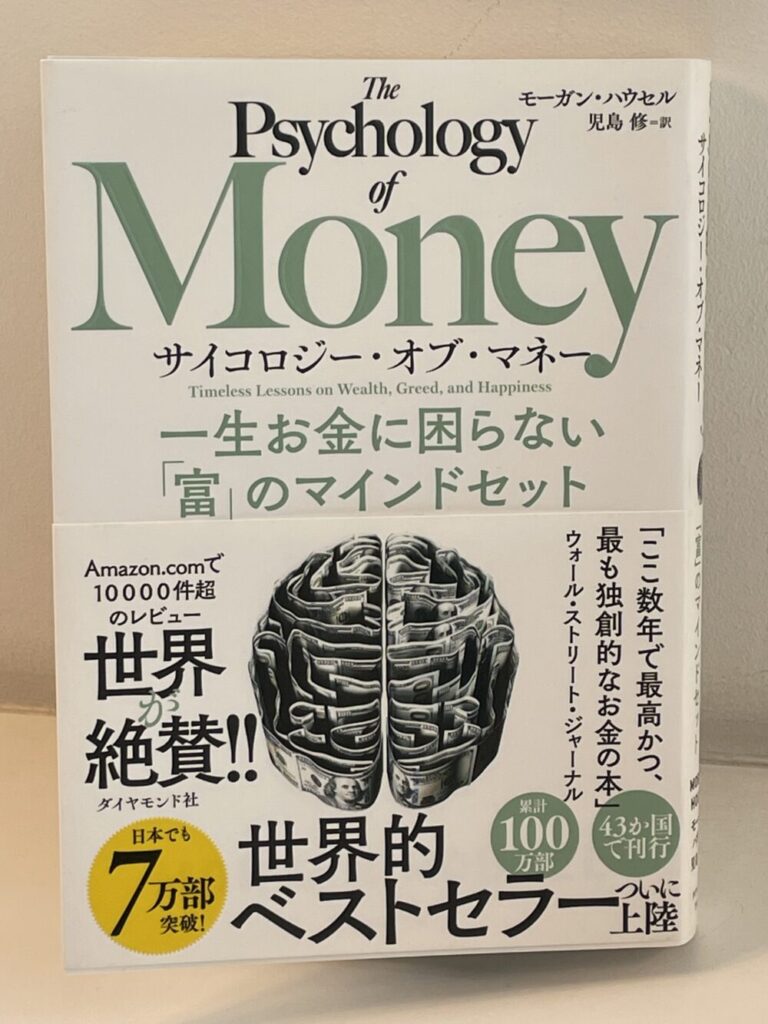
株式投資をするうえで、絶対ではないものの、いわゆる『最適解』と言われる答えは出ていると言われています。
『長期的にインデックス投資をたんたんと積み立てる』
でも、なぜそれができないのか、それを選ばないのか。
インデックス投資はもちろん購入しているけれど、ポートフォリオの全てをそれにできないのか。
世界的ベストセラーの書籍【The Psychology of Money(サイコロジー・オブ・マネー)-一生お金に困らない富のマインドセット-】を読んで、自分自身でも納得がいく一節がありましたので、自分なりに考察してみました。
最初に、この書籍について。
【The Psychology of Money(サイコロジー・オブ・マネー)-一生お金に困らない富のマインドセット-】は、ウォールストリートジャーナルの元コラムニストである【著者:モーガン・ナウセル】によって執筆され、世界で累計100万部超の大ベストセラーの書籍です。
日本では、2021年12月7日第一刷発行で7万部を突破しています。
「アマゾン.comで10,000件超のレビュー、世界が絶賛!!」
「ここ数年で最高かつ、最も独創的なお金の本」ウォール・ストリート・ジャーナル
と、本の帯では絶賛ぶりが強調されています。
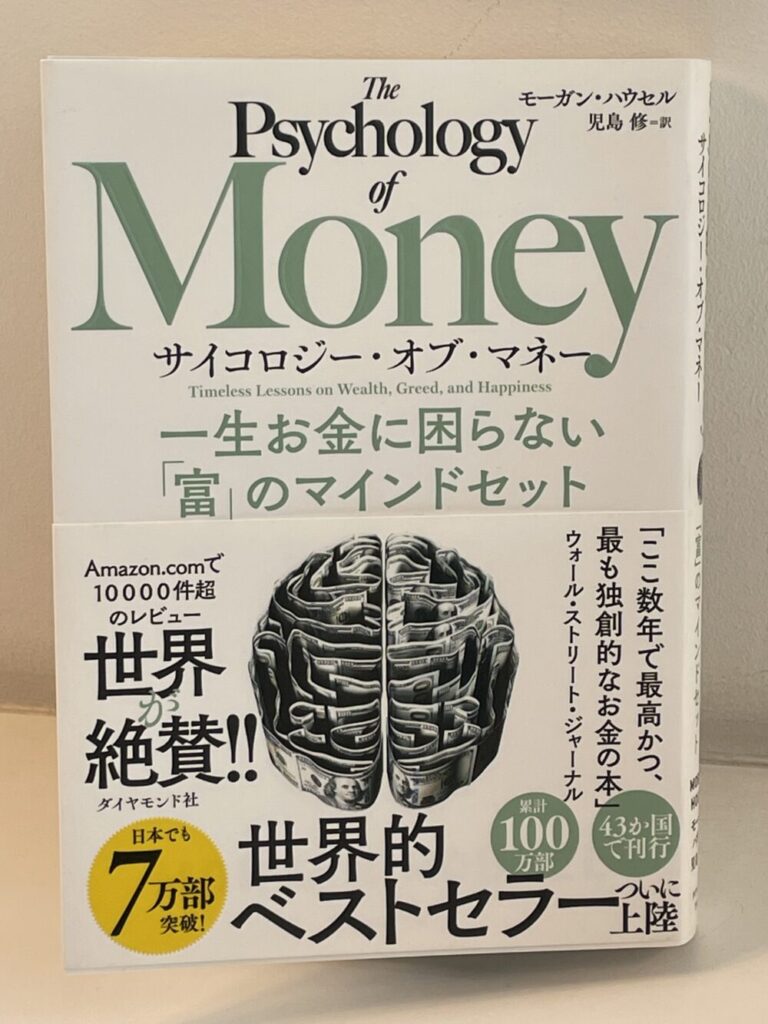
一つのテーマが長くなく、20のテーマにわかれており、読み進めやすい構成です。
ひとつひとつのテーマ、全てがいいこと書いていて参考になり、テーマに入る前の”はじめに”の冒頭部分のエピソードから引き込まれます。
今回は、第11章【合理的>数理的】ー冷徹な数理的思考より、おおまかな合理的思考がうまくいく=より、引用しながら考察していきたいと思います。
投資において、全米やS&P500の指数に連動した投資商品は大人気です。
投資で資産を増やす【最適解】とも言われています。
・数学的な計算上は、「長期のインデックス投資が一番資産が増える」とわかっているのにその行動がとれない。
・計算が得意な数学者でさえ、その行動はとれない。
・なぜか数学的より、心理学的に正しいと思う行動をとる。
例えば、
「配当金がチャリン、チャリン入ってくるのが嬉しいから高配当株投資が好き」
「株主優待が届くのが楽しみだから、家族も喜ぶから、株主優待投資をする」
「自分が好きな会社だから、その銘柄を買う。」
といった具合に、人それぞれに投資の行動は違うと思います。
投資を行う人は、共通して『資産を増やしたい』、『資産の最大化』が目的かと思われますが、とる行動はさまざまです。
上記3つの例のような投資をする理由があれば、それぞれの反論も正論のように存在します。
『配当金には課税されるから、資産の最大化を図るには投資効率が悪い、配当金から税金がとられずに再投資に回されるインデックス投資を積み立てるべきだ、減配リスクもある。』
『株主優待は改悪されるリスクがある。何万人という株主に優待品を送付する手間やコストにお金を使われるより、事業拡大や売上拡大に使われるべきだ。』
『好きな会社だとしても、決算資料など読み深め、ファンダメンタルズ分析など行ってから買うべき。』
といった具合に、絶対正しいとされる反論が存在します。
資産の最大化を考えたら、3つの反論は正論でまったくそのとおりだと思います。
数理的にも正しいので客観的に正しい。
いろんなデータ上も正しい。
これらの主張はごもっともで、わかっているはずなのに、その行動がとれない、もしくはとらない。
配当金が好きだから。株主優待が嬉しいから。その会社が好きだから。
数理的な正しさを勉強するのはとても大切だと思います。
資産を増やすうえで大切な要素は長期的に保有できるかです。
この長期的に保有できるか、その銘柄を持ち続けられるか、これを考えたときに心理的な要素が深く関わってくると思います。
「長期的に」と言うは易しです。
現実において、15年、20年という期間ではいろんなことが起きます。
株の世界における好景気や不景気の状況の変化。
日本中や世界中で起きる災害など。
自分自身の仕事、家計、健康、その時々の悩み。
家族の状況。
今から15年、20年遡って考えてみても、予想しない様々なことに直面してきています。
今後、予測もしない何かが起きても、その投資商品、その会社の株式を売らずに持っていられるかが大事になってきます。
この「長期でもっていられるか」を考えたときには、『数理的に正しい』とわかっていても、その知識だけでは長期保有できない人がたくさんいると思われます。
機会ではない人間ですから、感情の起伏があります。
その会社の株式を持っていられるかは、「自分で腹落ちしているか、納得できるか、夜安心してぐっすり眠れるか、含み損になったときに心がザワザワっとならないか」、これを知ることが大事になります。
心理的にどうかが、人それぞれ違うので、人それぞれ違う行動をとるのだと思います。
それが、それぞれに正しい。それぞれに合理的ということです。
【人は最善策ではなく腑に落ちる方法を選びたがる】
【「知らない企業」より「好きな企業」への投資がリターンを生む理由】
【保有している銘柄に『思い入れ』がないと困難に陥ったときに簡単に手放してしまう。】と著者は解説しています。
投資をするうえで、『思い入れ』なんていう言葉は客観的な判断を鈍らせるし、数理的に理詰めで考える人にとってみれば愚かな考えでしかないはずです。
ですが、この『思い入れ』があると、含み損になったときに簡単には売らないという行動がとれます。
それが結果的には、長期で保有することにつながります。
景気が良くても、不景気でもグリップ力が強ければ長期間持っていられます。
このグリップ力の原動力は数理的正しさではなく『思い入れ」により影響を受けるということだと思います。
これが長期的に投資のパフォーマンスを上げることにつながっていきます。
【最善策】であるはずなのに、インデックス投資が大きくマイナスになった数字を目にしたとき、このまま保有を続けていいのか迷ってしまう。
これ以上含み損が大きくなることに耐えられず、長期の保有ができずに売却してしまえばパフォーマンスは落ちてしまいます。
そこに『思い入れ』があると、大きなマイナスを見ても、好きな企業だから売らない、配当金がもらえるから売らない、株主優待が好きだから売らない、といった人それぞれに合理的な理由を見つけて保有していられます。
結果的に長期で保有し続けられて、数理的に正しい判断のみをしていたときよりパフォーマンスが上がる。
こういったことを、著書では解説されています。
【個別株投資は勝てる見込みが薄いため、ほとんどの人にとってこれは、計算上、理にかなった選択ではない。しかし、基本的には分散投資をしておいて、どうしてもこだわりたい企業へ少額を投資するのは合理的だと言える。】
自分自身、具体的に落とし込めば、つみたてNISAやiDeCoにおいて、インデックス投資をつみたてし、高配当株や株主優待、または好きな商品やサービスを提供している会社を楽しみながら少し買うというのが、長く投資を続けるコツだと理解しておくのがいいのではないかと考えています。
株式投資の魅力は、長期保有し老後の資産を最大化するだけではないと思います。
老後資金だけではなく、今も楽しめます。
それが、配当金や株主優待だと思っています。
配当金をもらって、お金がお金を生む実感を知り、そのお金で美味しいごはんを食べたり、自由に使ってもよし。
その配当金でまた同じ銘柄を購入すれば配当金再投資となり、次の配当金が増えるのも楽しいです。
配当金を再投資に回さなくても、会社が増配してくれるときもあり、これも嬉しい瞬間のひとつです。
最初は小さい金のなる木でも、少しずつ大きく成長していく実感がわきます。
配当金で入ってくる金額を考慮に入れとけば、株が多少マイナスになっていても、心がざわつかず気にしないでいられます。
このへんの感覚は、実際に株式を購入し実際にマイナスの数字を見たときに、自分がどういう精神状態になるのか、どのくらい気持ちが揺さぶられるのか体感しないとわからないところです。
そのため、少しの金額から投資を始めるという重要性がわかります。
株主優待の魅力。
株主優待自体には、廃止するべきといったように、確かに賛否両論あります。
配当金も株主優待も両方ある銘柄はたくさんありますので、利用しない手はないと思います。
株式を購入し、実際に優待品が届いたとき、めちゃくちゃ嬉しいものだなと思いました。
数年は経験しましたが、今でも嬉しいものです。
カタログが届いて好きな商品を選んだり、その会社のオリジナル商品が届いたり、家族で楽しめます。
利用できる商品、サービス分の支出が減るわけですから、株主優待だって家計管理、資産拡大に役立つことには変わりないです。
世界的大ベストセラーの【The Psychology of Money(サイコロジー・オブ・マネー)-一生お金に困らない富のマインドセット-】。
投資において、人それぞれに正しいと思った正解がある、合理的な判断があるということをあらためて教えてくれる一冊でした。
インデックス投資か高配当株投資か、お悩みの方には、とても参考になる名著だと思います。
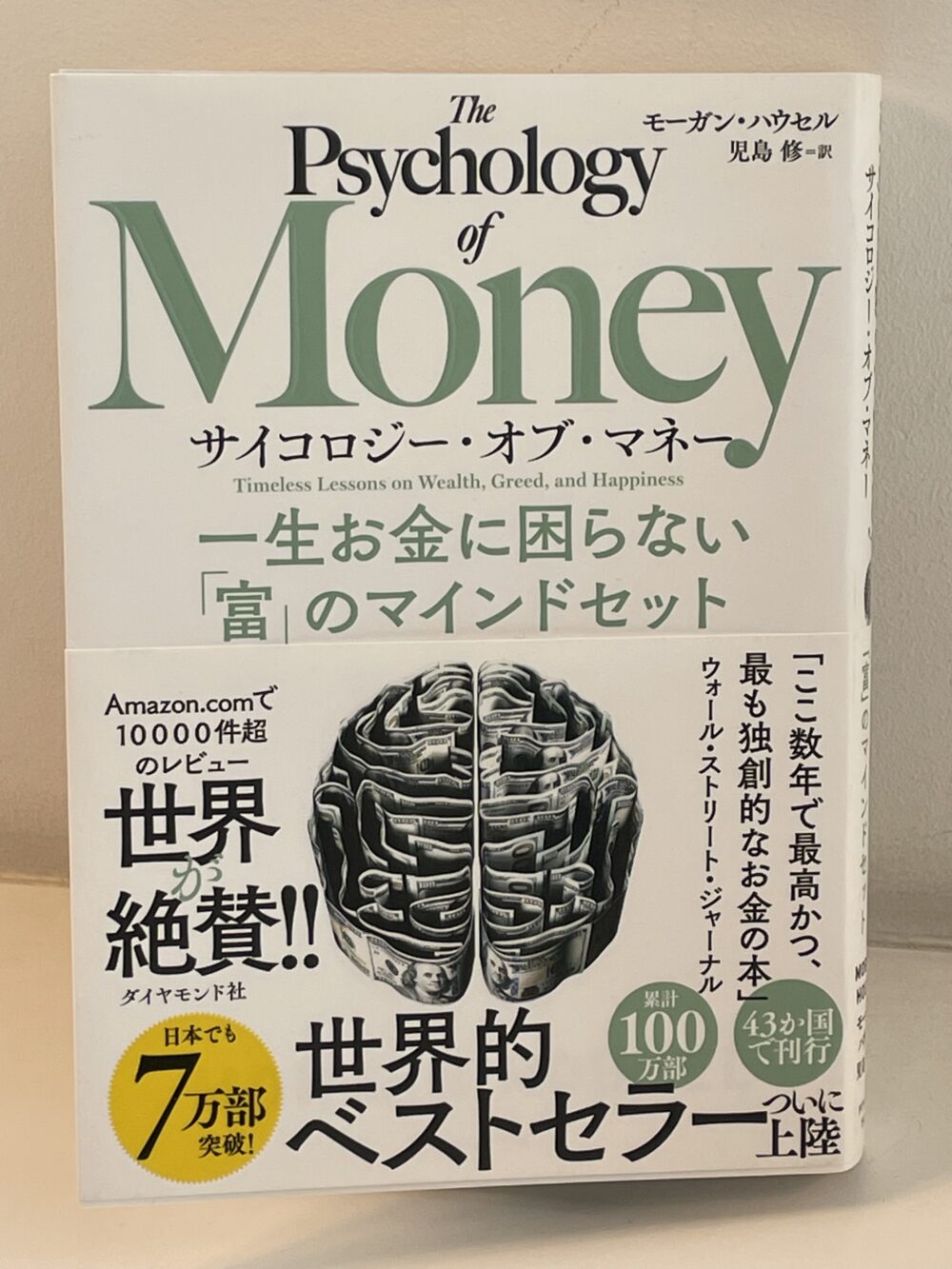


コメント